ホーリー先生の外資系キャリア塾:成功の掟〈最初の90日がすべてを決める。オンボーディング成功編〉
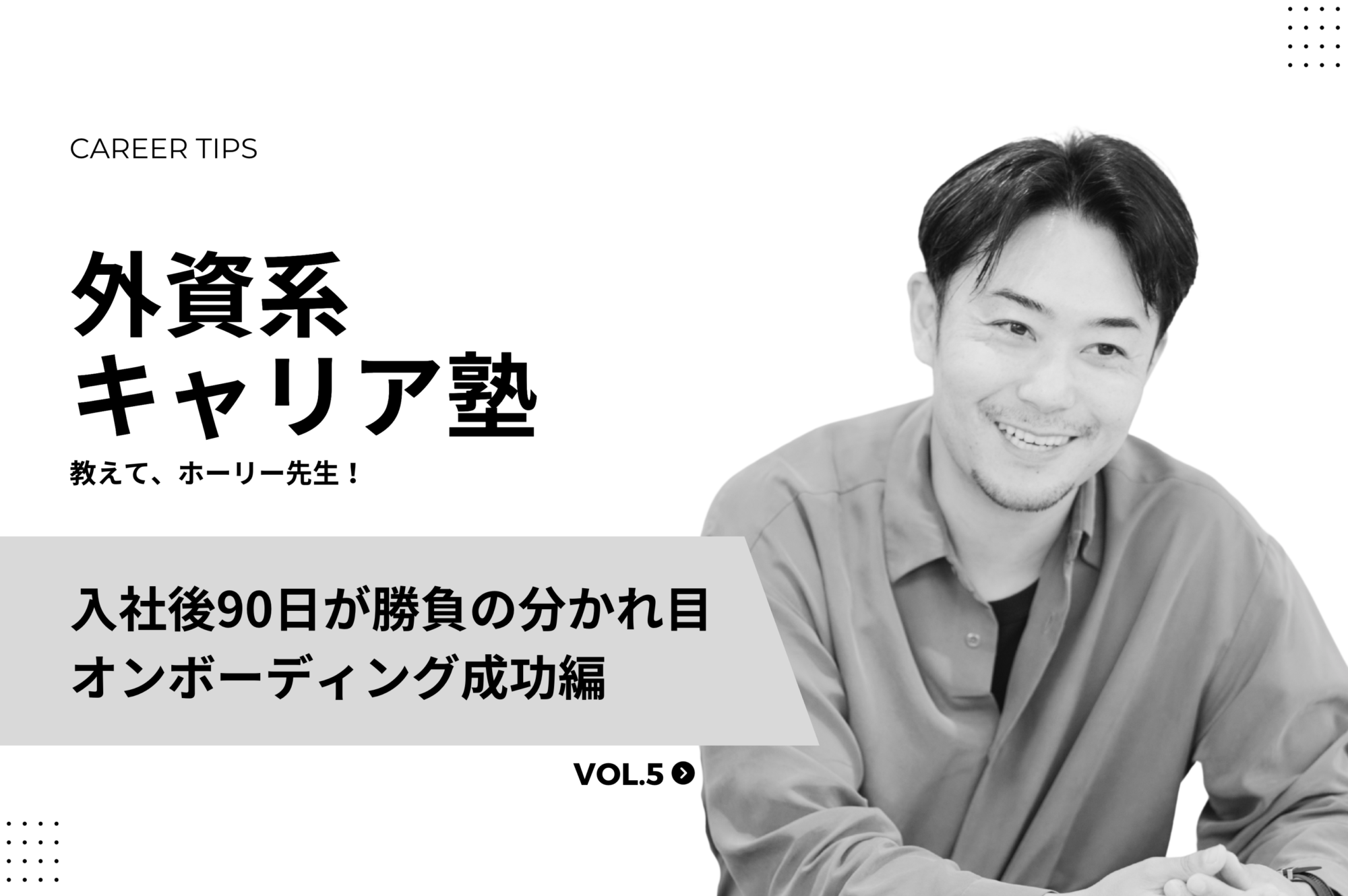
外資系企業において、入社後、最初の90日が勝負と言われている。信頼関係の構築やカルチャーの理解、成果の創出などが求められ、それに応えることができなければ、雇用契約の見直しをせまられる可能性も十分あるためだ。では90日という短期間で、何を意識し、どのように行動すればよいのか。前回の面接編でも解説したホーリー先生に、オンボーディング成功の戦略を聞いた。
堀 弘人さん(ホーリー先生)/H-7HOUSE LLC 代表 | ブランド・マーケティングコンサルタント
独立系マーケターやクリエイターと連携する H-7HOUSE (エイチセブンハウス)を創設し、企業の経営課題や社会課題に対するブランド・マーケティング戦略を推進する。 「PEOPLE BASED BRANDING®︎」 を提唱。 人的資本を活かしたブランド構築を実践し、「人」を軸にしたブランド価値の最大化を支援する。 外資系ブランドでマーケティングディレクターを経験し、日系上場企業の国際戦略部門にて、新規事業の立ち上げと短期間での収益化を実現した実績を持つ。 ブランド戦略を経営視点で捉え、事業成長とブランド価値の最大化を両立させるコンサルティングを強みとする。
「90日間が勝負」とされる理由
― 外資系企業で、入社後の90日が重要だと言われるのはなぜでしょうか。
この90日は、仕事に慣れるための準備期間ではなく、即戦力として成果が出せるかの「適性を見極める期間」です。そのため、成果の兆しが見えなければ、契約の見直しをせまられたり、打ち切られる可能性がゼロではありません。海外映画でよく描かれるように、朝に突然解雇を告げられ、午後には段ボールに荷物を詰めて退職するというケースも外資系企業においては現実的に起こりうるのです。
また外資系企業の「即戦力」とは、Day1(入社初日)から自ら考え、動き、成果を出すこと。さらに心理学でいう初頭効果もあり、入社直後の印象や成果は、その後の評価に強く影響します。まさに「勝負の90日」といえるでしょう。
― 90日間、意識すべき点について教えてください。
大きく分けると、「信頼関係の構築」「カルチャー理解」「成果の創出準備」の3つを同時に進めることが重要です。まずは周囲の声に耳を傾け、組織が何を課題としているのかを正しく把握すること。次にその文化や価値観を理解し、自分がどう適応するかを見極めること。そして、早い段階で今後見込める成果を提示し、存在意義を示すことです。この3つをバランスよく実行できるかどうかが、その後の評価を大きく左右します。
「傾聴」と「主体性」の両立で信頼関係を築く
― 入社直後、信頼関係を築いていくうえでのポイントを教えてください。
「傾聴」と「主体性」を両立させることです。傾聴や観察で、自分の期待されていることやチームの課題を理解します。暗黙知のような気づきづらい課題もありますので、それらをできるだけ早くキャッチアップすることが、最初の重要なステップです。
しかし、傾聴だけに終始すると「受け身な人材」と見なされてしまうリスクがあります。「即戦力採用」が前提なので、傾聴で得た情報を踏まえて、自分なりの行動計画や改善提案を示すことが重要です。受動と能動をかけ合わせる姿勢こそが、信頼を築く第一歩となるでしょう。
加えて、外資系企業では「引き継ぎなし」というケースも珍しくありません。前任者がすでに退職している、あるいは海外に異動して時差で連絡が取りづらい、といった状況もよくあります。だからこそ、Day1からフルスロットルで動ける機動力が要となります。
― 上司や同僚、部下など、それぞれの立場の方々とどのように関係を築いていくとよいでしょうか。
上司に対しては、1on1ミーティングを自分から提案して早い段階で期待値をすり合わせたり、部下や同僚に対しては、日常の会話や雑談からコミュニケーションをとり、安心して意見を言える雰囲気をつくることが重要ですね。例えば、ランチやコーヒーチャットといったカジュアルな接点は、相手の人柄を理解し、心理的な距離を縮める効果もあります。また他部署に対しては、共通のプロジェクトなどをきっかけに接点を増やし、早めに協力関係を築いておくのも有効的です。
― 外資系企業ですと、日本以外の方との関係構築も必要となりそうですね。
まさに外資系特有のポイントとして、本国オフィスとの関係構築も外せません。意思決定権が海外にあることも多く、日本オフィスだけで成果を上げるのは難しいのが実情です。アジア拠点や欧米本社などと早い段階から接点を持ち、準備をしておくことが大切です。
新しい組織文化に適応するための心構えとは
― 組織のカルチャーに適応する際の注意点を教えてください。
前職の常識や価値観を、そのまま新しい職場に持ち込むのは避けるべきです。以前の環境では当たり前だった進め方や判断基準であっても、組織が変われば通用するとは限りません。その違いを理解しないまま従来のやり方を適用すると、周囲から「文化を理解していない」と判断され、協働がスムーズに進まなくなる恐れがあります。
私自身も過去に、文化の違いで苦しんだ経験があります。転職前の会社は「革新性が重視される文化」でしたが、転職後の会社は「伝統を重んじる文化」でした。文化の違いを理解せず、以前の考え方をそのまま持ち込んだ結果、最初はうまく適応できないばかりか、不要な摩擦や軋轢を生んでしまったこともあります。
― 文化の違いに直面したとき、どのような姿勢で臨むとよいのでしょうか。
最初の1〜2ヶ月は「教えてください」というスタンスで臨むのがよいでしょう。まずは相手の価値観を理解する、学ぼうとする姿勢を見せることが、信頼関係を築く第一歩です。
観察を重ねていくと、会議の進め方や承認フローなど、組織特有の改善すべき暗黙知に直面することもあるでしょう。違和感を感じてもすぐに声を上げるのではなく、まずは相手の意図を理解しようとする。そして、信頼関係が構築されたときに、しっかりと提案できるよう記録しておきます。
また改善点については、目標や成果報告などのタイミングで提案することで、信頼を損なうことなく組織に変化を促せる可能性があります。
期待値の調整が、90日後の評価を決める
― 即戦力採用の外資系企業で、90日以内に成果を示すための具体的な行動を教えてください。
1ヶ月、3ヶ月といった節目で自分なりに整理し、目標や戦略と一緒にプレゼンテーションします。というのも、入社直後に提示されるKGIやKPIは、多くの場合ストレッチゴールです。3ヶ月で到達できず、正しく評価されないケースもあります。
そこで、私は次の2ステップで成果を示すことをおすすめします。
ステップ①入社後1ヶ月以内:成果を分解する
- 3ヶ月以内に達成可能な「クイックウィン」を定量的に設定する
- 中長期(6ヶ月・12ヶ月)で取り組む課題と仮説を設定する
- 組織理解・人脈構築・カルチャーフィットなど質的な改善成果も設定する
ステップ②入社後3ヶ月以内:成果を提示する定期的な1on1で進捗と方向性を透明性をもって進捗や成果を共有する
- ゴールだけでなくプロセスや考え方も説明し、認識を揃える
- 達成した(する見込みの)数字は量的に表現し評価にブレがない状態に。また質的な成果についても必ず提示する
ステップ①では、1ヶ月で得た課題感や組織理解を共有し、その課題から見える短期的な貢献を提案をします。同時にその限られた情報から、中長期で取り組む課題解決のための仮説を構築しておくことも重要です。仮説を追いながら日々の行動計画を立てることで、どこに自身のリソースを配分するか意思決定がしやすくなります。
ステップ②では、3ヶ月間で見えてきた本格的な課題の解決策、つまりは戦略を提示します。完璧な戦略でなくても「考え抜いた上で方向性を示せる人だ」と認識され、組織のリーダーシップとして信頼につながります。3ヶ月目には、本国オフィスや自国内組織との連携を取りながら自分なりの戦略を形にして見せることが重要です。逆にいうと3ヶ月以上の時間をかけると状況把握が遅い、アジリティが低いなどというレッテルをはられることもあります。
― 期待値を設定するうえで、ホーリー先生が気をつけていることはありますか。
特に意識すべき点は「データを根拠に語る」ことです。例えば市場調査や競合比較の数値を示し、「現状では売上を200に伸ばすのは非現実的だが、170〜180程度であれば達成可能」といった形で、客観的な根拠やエビデンスをもとに説明します。データを用いて現実的な到達点を共有することで、過大評価や過小評価を避け、組織内での信頼を維持することができるのです。
― 最後に、オンボーディングがうまくいく人は、どんな人でしょうか。
外資系企業におけるオンボーディングとは、「受け身」で終わるのではなく、「設計」し「主導」するプロセスです。最初の90日で信頼を築き、文化を理解し、成果を可視化することで、自分の存在意義を明確に示せる人が成功するといえます。
重要なのは、早い段階で周囲にポジティブな影響を与えることです。小さな提案や成果でも「この人と一緒に働きたい」と思わせられる人は、変革者として歓迎されます。最初の90日間の行動が、あなたのキャリアを大きく左右するといっていいでしょう。
文:金井みほ